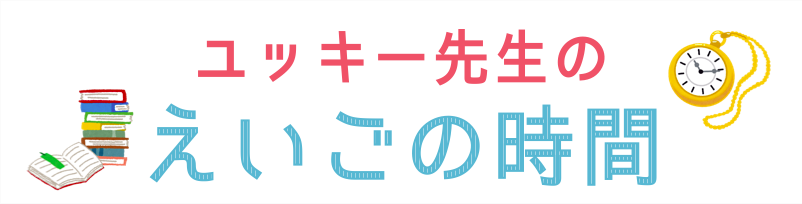【解ける?】文学者、ボブ・ディランが曲に仕掛けた7つの言葉遊び。
ノーベル文学賞受賞後も沈黙を貫くボブ・ディラン。
その代表曲の一つを直訳・意訳してみました。

出典:telegraph.co.uk
文学者、ディランの仕掛けた言葉遊び。
7つの観点から分析してみたいと思います。
ぜひ今日は、謎解きに挑戦するような気持ちで読んでみてください。
じっと見つめれば見つめるほど奥が深すぎる、
文学×音楽の世界にどっぷりです。
沈黙を貫くボブ・ディラン
- 沈黙を貫くボブ・ディラン
- 何がそんなに凄いの?“文学賞”受賞の理由は?
- 【朗読で感じる】”Don’t Think Twice, It’s All Right.”
- 1. ちょっとワルな表現”ain’t”にかかる二重否定
- 「二重否定」2つの役割
- 2. 声に出した時にリズムをつくりだす【韻(rhyme)】の仕掛け
- 「歌詩」を書く人、ボブ・ディラン。
- 3. え、この文法は一体何!?古英語からの「a-動詞ing」形
- englishforums.comで聞いてみる
- 4. know-knew-knownではなく「knowed」古いけど正しい英語
- 5. a-動詞ing形、ふたたび。
- 6. 考えさせられる、深すぎる言葉選び。男女の恋愛観。
- 7. 英語で見て初めてわかるディランの仕掛け!Goodbyeは「グッドな」さよなら。
- 【動画で見る】英語で朗読!「くよくよするなよ」日本語訳付き。
- ボブ・ディランが歌う「くよくよするなよ」はこちら

こんにちは!ユッキーです。
久しくブログを更新していませんでした!
約2週間。こんなに日が空いてしまったのはブログを初めて以来初のこと。9月末のイベントや英検、スギーズJr. 先生の書籍キャンペーンが終わり、少しほっと一息つきながら、今後のブログや動画の方向性についてじっくり考えていました。動画用に使えそうなアイテムを買い揃えたりもしました。(いろいろと面白いものを揃えたので、きっと楽しんでいただけると思います♪)
ちなみに上の写真↑ は自分の判断でお蔵入りさせた「ボブ・ディランを歌ってみよう」動画。撮ってみたのですが、わかりづらかったり、イマイチまとまりがなかったりしたのでボツにしました。そんな、実験?試行錯誤もしていた2週間でした☆
さてそんな「沈黙」のような状態にあった私ですが【沈黙】と言えば最近もっぱら話題なのがボブ・ディランですよね!
・辞退するのではないか
・そもそも、ノーベル賞自体を認めていない
・ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルの賞を、ディランが受け取るはずがない
ノーベル賞事務局側の電話に返答しない理由に対して様々な憶測が飛び交っています。
↓海外では、こんなタイトルまで付けられて報じられているそうです。
ノーベル賞事務局側の「ドアノック」に無言を貫くディランについて書いたCNNの記事。"Knock, Knock, Knocking on Heven's Door" にひっかけたタイトルです。英語だととこんな面言葉遊びができるんですね!https://t.co/vuGbWSasWL
— ユッキー@英語教材プロデューサー (@yukki_eigo) October 19, 2016
事務局側の「ドアノック」に対して彼がドアを開く日はくるのでしょうか…?
何がそんなに凄いの?“文学賞”受賞の理由は?

出典:japantimes.co.jp
そんなボブ・ディラン。「詩がとにかく文学的」「抒情的な音楽」と言われているようですが、具体的に一体どんなところが文学的なのでしょう?どうせなら、英語で英語のまま、その凄さを感じてみたいですよね!
【朗読で感じる】”Don’t Think Twice, It’s All Right.”


出典:images-na.ssl-images-amazon.com
出典:thevinylfactory.com
今日はそんな彼の作品の中から、2作目のアルバム「FREEWHEELIN’」に収録の「くよくよするなよ(=Don’t Think Twice, It’s All Right.) 」の歌詞を使って、彼の文学性を紐解いていきたいと思います。「風に吹かれて(=Blowin’ In The Wind)」や「はげしい雨が降る(=A Hard Rain’s a-Gonna Fall)」といった名曲がある中で、あえてこの曲を選んだのは、テーマが【恋愛】であり、歌詞の内容やストーリーにも身近さを感じていただけるかな、と思ったからです。
朗読してみました。

歌詞の内容を、しっかりと感じるために。「歌ってみた」ではなく「朗読して」2分半の動画にしてみました!(動画は記事の最後から御覧ください↓)その中でも特にディランの文学性を際立たせているポイントを7つ、今日はこのブログで分析していきたいと思います。
※2週間ぶりのブログ。長いですがいつも以上に英語について考えられるような中身にしてみました。気軽に読むも良し、腰を据えて読むも良し、楽しくスクロールしていただけると嬉しいです。それでは、行ってみましょう!
1. ちょっとワルな表現”ain’t”にかかる二重否定

さて歌い出しに早速入っているのは it ain’t no use to〜の表現。ちょっと入り組んだ英語表現です。この後も曲の中で何度も繰り返されるので、しっかりと見てみましょう!
◆ain’t
=am not/ is not / are notの短縮形
Well, it ain’t no use to sit and wonder why, babe.
=Well, it isn’t no use to sit and wonder why, babe.
(日本語訳)
まぁ、座り込んで悩んだって意味なんかねぇよ。
ちょっとワルでヤンキーっぽい印象を与える言葉づかいで、現代でも使われています。ain’tは歌の中でよく使われる表現でもあり、同じく有名なのがこの曲♪
Marvin Gaye & Tammi Terrell
“Ain’t No Mountain High Enough”
朝の通勤時や「さぁ、何かはじめるぞ」「これからこれから」という時に聞くと、すごく気分が上がる1曲ですね⛰^ ^
◆ain’t no use to〜
=is not no use to
そしてここで押さえたいもう一つのポイントがこれ。一度notで否定しているのに、その直後にまたnoが続き、否定が2つ重なっています。これは「二重否定」の表現ですね!「あ、二重否定って否定を打ち消すことで肯定に変わって肯定としての意味が強調される表現のことでしょ!」と思われた方、必ずしもそうとは限らないんです☝
「二重否定」2つの役割
その1:
(−)×(−) = +
→肯定を強調する役割
(例)
There is nobody who doesn’t know his name.
= Everybody knows his name .
彼の名前を知らない人は居ない。
=みんな彼の名前を知っている。
否定(nobody)×(doesn’t)の掛け合わせによって、意味が(+)になり「知っている」という肯定的な印象を強調する役割です。おそらく学校の英語の授業で習ってきたのはこのタイプ。そして通常「二重否定」を使う場合、ほとんどのケースはこの役割です。ですが、こういった場合もあるんです↓
その2:
(−) × (−) = −
→否定を強調する役割
(例)
I can’t get no satisfaction.
満足が全くないものなんて得られない。
=???満足がある???
ん?????
なんだかよく訳せませんね😗
この場合、日本語訳として正しいのは「満足感なんてこれっぽっちも無い。」という否定を強調した表現。
ちなみに今の例文は…
…そうです♪ローリング・ストーンズでした〜🎸
後に続く歌詞の意味からみても「とても満足している」という肯定の強調は有り得ないんですね。こういった【否定を強調する二重否定】は、日常会話ではあまり馴染みがありませんが、歌詞や詩の世界ではよく登場するようです。二重否定といえば「肯定の強調」と一点張りで覚えるのではなく、否定が強調されるケースもあることを少し頭の片隅に置いておきたいところです☝
少し長くなってしまいましたが、Don’t Think Twice, It’s All Right.に出てくるIt ain’t no use to〜の二重否定も、ローリング・ストーンズの場合と同じく、否定を強調する二重否定。「全然意味ないよ」の強調です。
2. 声に出した時にリズムをつくりだす【韻(rhyme)】の仕掛け

crows(クロォウズ)とwindow(ウィンドォウ)、dawn(ドォン)とgone(ゴォン)のように、歌詞の中で頻繁に韻が踏まれています。このような「韻踏み」は歌詞というよりは通常、英語詩の中でルールとして用いられます。日本の俳句でも【五・七・五】や【季語を入れる】といったルールがありますが、英語の詩の世界にも【韻を踏む】というルールがあるんですね。
「歌詩」を書く人、ボブ・ディラン。

出典:wennermedia.com
そのルールを「詩」で適用するのは普通、というより当然のようなことなのですが、ディランの場合は歌手であり「歌詞」を書いているにも関わらず、「詩」の世界に存在する【韻を踏む】というルールをかなり徹底して楽曲の中に入れ込んでいるところが特徴的です。今日ご紹介している”Don’t Think Twice, It’s All Right.” 以外の曲でも、彼の曲を聞いてみると、見事に韻だらけ!踏みっぱなしのわかりやすいものから、隠したように踏まれているものまで、あちらこちらで韻が踏まれています。これこそ、他の歌手にはあまり見られない彼独自の特徴であって、加えてその韻の感じが彼の歌声やメロディ、伴奏と見事にマッチしていることから「詩を抒情詩人のように歌う人」として評価されている部分もあるんですね。
どんな歌手でもとにかく韻を踏めば文学的になるかというとそんなわけではなく、一言で韻を踏むといっても、どの単語を使って韻を踏むのか?言葉選びの才能もなければいけないので、そう簡単にはいきません。ディランだからこそ生み出せる音楽、文学。言うなれば彼が書いているのは「歌詞」ではなく「歌詩」なのかもしれません。
3. え、この文法は一体何!?古英語からの「a-動詞ing」形

今回英語を見ていく中で、ちょっと困ってしまったのがこの表現。
【a-traveling on】
traveling onではなくて?
最初「何かの間違い?」「歌っている通りに書き起こした英語なのかな」と他の歌詞ページもいくつか見てみたのですが、どこもa-traveling onでした。一体何なんだ、このaにハイフン、動詞の形は…と思い、調べてもよくわからず。どこにもヒントが無かったので、人に聞いてみることに。
englishforums.comで聞いてみる
https://twitter.com/yukki_eigo/status/788534136306741248
◆質問 (わたし)

こんにちは。「Don’t Think Twice, It’s All Right.」の中で、なぜボブ・ディランが「You’re the reason I’m traveling on」の代わりに「You’re the reason I’m a-traveling on」と書いたのか、その理由がわかる方はいますか?
「a」は彼が旅に出て行く宛てもなくさまよっていることを強調しているためにつけられているのかなと思ったんですが、どうですかね?
◆回答(Calif Jimさん)

違います。ここで使われている「a」は、名詞の前につく冠詞としての「a」とはまた別物です。
動詞の-ing形は古英語の時代に、よくaと一緒にセットで使われていました。私の記憶が正しければ、特に移動動詞で用いられることが多かったようです。「a」と「ing」を使った表現は今でも田舎の方で残っています。
言葉をより「庶民的」だったり「田舎っぽく」するための、ディランの工夫なんだと思います。
この質問に答えたら、私もちょっとぷらついてこようかな。
CJより
a-travelingの表現は、ディランの思いつきで創られた英語ではなく、れっきとした【正しい英語】だったんですね。でも、現代ではほとんど使われていない古い英語。それを敢えて歌詞に入れ込む文学性もまたすごいです。
4. know-knew-knownではなく「knowed」古いけど正しい英語

I never knew ではなく
I never knowed
「know」の活用形といえば【know-knew-known】ですが、これは現代に至るまでに出来上がっていった英語の形。古くからずっとこの形だった、というわけではありません。昔は「know」も不規則動詞ではなく、シンプルに-edを付けて過去形や過去分詞形にする動詞、として使われていたんですね。先程のa-travelingと同じく、ディランが意図して使っている「古英語」的表現です。
5. a-動詞ing形、ふたたび。

ここでも出てきました!しかもこんどは2連続。メロディに乗ると、更にa-の表現が際立ちます。この表現は、歌詞の中だけでなく曲名としても用いられることがあり、同じアルバムに入っている「はげしい雨が降る(=A Hard Rain’s a-Gonna Fall)」でもa-Gonna Fall 、使われている形なんですね。「ん?ingの形じゃないじゃん」と思われた方、よ〜く見てください。Gonnaは「going to」のことです。動詞+ingですね♪
6. 考えさせられる、深すぎる言葉選び。男女の恋愛観。

“I gave her my heart
but she wanted my soul“
(日本語訳)
僕は彼女に「heart(心、ハート)」をあげた。
でも彼女は僕の「soul(魂、ソウル)」を欲しがった。
よく「恋愛において男女が求めるものは違う」なんていうことを聞きますが、この一節もそうなのかなと思いました。heartとは一体何を指していて、soulはどういったことを示すのか?気持ちだけじゃ通じなかった、ということを言っているのか、彼女が求めたのは熱いハートではなくもっと堅実的な未来だったのか?答えがわかるようでわからないような面白さがあります。みなさんはどう捉えますか?
7. 英語で見て初めてわかるディランの仕掛け!Goodbyeは「グッドな」さよなら。
さてここまで、1〜6まで。私が特に気になった英語表現をご紹介してきました。でも一番好きだったのはこの一節です。
Goodbye’s
too good a word, babe
これをそのまま日本語に訳すと「さようならは良い言葉すぎるから」という訳になるのですが、これを英語のまま見てみると【goodbye】は「good」と「bye」に分けることができ、そんな風に「good」が入っている言葉を、別れ行く僕達の「さようなら」の言葉として使うのはあまりに良い言葉すぎるから、という奥深くに隠されたメッセージが見えてくるんです。
英語を英語のまま見ないと、決して見えてくることのない“ディランの仕掛け”なんですね!
【動画で見る】英語で朗読!「くよくよするなよ」日本語訳付き。
ぜひみなさんも、音読してみてはいかがでしょうか♪
ボブ・ディランが歌う「くよくよするなよ」はこちら
最後までお読み頂いた皆さん、ありがとうございました🍑
7つの仕掛け、いかがでしたか?
授賞式の行方が気になるところですが、他の曲もたくさん聴いてみたいと思います♪
フレーズ、おぼえよう!
▶︎WEB限定!5日で50フレーズを記憶できる!CD音声無料プレゼント